こんにちは、「くりん」です。
2022年の半年間、愛猫「かりんとう」は闘病生活を送ったのち、10月11日の明け方に旅立ちました。
前回は、保護猫の「くりきんとん&かりんとう」が我が家に来るまでのお話でした。
今回からは、「かりんとう」との闘病生活を振り返って書いていこうと思います。
異変に気づいた、6月。

「かりんとう」の異変に気づいたのは、6月のある夜のこと。
最近、たまに透明の液を吐くな〜とは思っていました。
ただ、ご飯はよく食べていましたし、おやつの催促もしていたので様子を見ていました。
「かりんとう」は、食べることに執着があるタイプです。
小さい頃が過酷な環境だったせいなのかもしれません。
相棒の「くりきんとん」のごはんも自分のものかのようにいつも奪って食べていました。
一方、「くりきんとん」は面倒見のいいお兄さんタイプで、ごはんを取られても怒らず、
むしろ譲ってしまう性格です。
シェルターにいる時も、まずは仲間の皆んなが食べるのを見守り、自分は残ったご飯を食べていたそうです。
我が家でも、まずは「かりんとう」が食べ始めるのを確認した上で自分も食べていました。
本当に世話好きの優しい兄猫です。
2022年6月のある夜のこと。
食いしん坊の「かりんとう」が大好きなごはんを目の前にしても食べようとしません。
元気もない様子。
気づいたのは夜の8時過ぎだったと思います。
何かがオカシイを思った私は、かりんとうを洗面所に追い、洗濯ネットで捕まえて、すぐに病院へ向かいました。
「かりんとう」はこの頃は、人間にも心を許し、身体を撫でさせてくれるまでにはなっていましたが、抱っこをしたり、捕まえたりすることは困難な猫でした。
そんな「かりんとう」を無理矢理捕まえて病院へ。
病院へは過去に1回だけ連れて行ったことがあります。
顎の下を掻きむしって血だらけにしたことがありました。
体調が悪いのか、病院が怖いのか、
ゲージに入ってしまえば、毎回とてもいい子に大人しくなる子でした。
ウーッともシャーッとも言わずにじっと待合室で一緒に診察を待っていました。
病院が開いているうちにと、急いで家を出てきたので、
家に残してきた「くりきんとん」は不安がっていたことでしょう。
診察の結果

診察の順番が来て、診察室へ。院長先生でした。
「かりんとう」の様子を伝え、身体や口腔内を見てもらうと、
- 重度の歯周炎(口内炎・歯周病)
- 黄疸
であることがわかりました。
体重も3.9kgと痩せて軽くなっていました。
いつの間にこんな酷い状態になっていたのか…
毎日一緒に過ごしていたのに気づいてあげることができなかった自分を責めました。
採血をし、結果を待ちました。
長い待ち時間、夫にはなかなか連絡がつかず、母に連絡をしながら、不安な時な時間を過ごしました。
「かりんとう」は狭いゲージの中、病院の長い待ち時間で身体はしんどかったでしょう。
思い返せば、症状として
- 体臭、口臭がある
(体臭は「かりんとう」独自のものだと思っていましたが、歯周炎によるものだったのですね。) - たまにある嘔吐
- よだれ
- 下を出している
- 寝ていることが多い
こんなことがありました。
採血の結果

初回に来た病院は、人気のある動物病院ではありますが、とにかく待ち時間が長いです。
この日も、来院〜帰るまでに診察、待ち時間含めて2時間ほどかかったと思います。
携帯で色々と調べながら待っているうちに、採血結果が出て再び診察室へ。
結果は、
- 白血球数の高い値
- 肝臓の数値の高い値
- ビリルビンの高い値
- アルブミン値の低値
- 脱水
また、”胆管炎”を起こしているという診断でした。
黄疸、胆管炎、肝機能の悪化から、猫にとって怖い病気である
『肝リピドーシス』の疑いがあるという診断が降りました。
ただ、胆管炎には、
①細菌感染が直接関与する「化膿性胆管炎・胆管肝炎」と、
②自身の免疫細胞であるリンパ球などの関与が原因とされる「非化膿性胆管炎・胆管肝炎」
の2つの原因があり、どちらが原因かで治療法が異なるとのこと。
私は『肝リピドーシス』という病気を、そこで初めて知りました。
人間の脂肪肝は、生活習慣の乱れ(食べ過ぎ、飲みすぎ、運動不足など)によって患う方が多いとされていますが、
猫の場合は、数日間の食欲不振、絶食が続き、たんぱく質が不足した状態になると、体の中の脂肪代謝が阻害され、それが引き金となって脂肪肝を発症することが多いそうです。
肥満の猫に多い病気だそうですが、「かりんとう」はよく食べますが肥満という体型ではなかったと思います。
ストレスや重度の歯周炎(口内炎)のせいで、うまく食事が摂れていなかったのかもしれません…
先生より、口内炎の治療としては特効薬(ステロイド)があるとのお話がありましたが、ステロイド剤なので内臓に負担がかかる副作用もあり、原因が特定できていない現状では使えないとのこと。
ただ、この時の「かりんとう」の状態は非常に悪く、胆管炎の原因を特定する検査(細胞検査)をすることはできませんでした。(麻酔をかける必要があるため)
また、歯科治療(抜歯)も麻酔のリスクを伴うためできませんでした。
この日の「かりんとう」の状態から、今後の治療方針としては、肝リピドーシスを想定して「食べさせること」「栄養を摂取すること」と言われました。
この日は、少しの日か点滴をしてもらい、自力での摂取が難しい場合は強制給餌をしてくださいとのことで、お試しでヒルズのa/d缶とシリンジをもらいまいた。
薬は、ウルソデオキシコール酸が処方されました。
強制給餌の開始。〜準備〜

動物病院から帰宅し、夫と「くりきんとん」と会いました。
まさかの結果に、私も主人もとてもショックを受けました。
なにより、重大な異変に気づいてあげられなかった事に、「かりんとう」に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
猫は不調を隠すのが上手な生き物です。
日々の些細な変化に気づいてあげることが大切なのはわかっていたのに。
普段入らない、狭いゲージに入ったりして合図をくれていたのに、コロナ禍での仕事の忙しさや、「かりんとう」の性格を理由に病院に連れて行ってあげられなかった飼い主の責任です。
私たち夫婦は、まずは出来ること「強制給餌」をやろう。と決めました。
この頃のかりんとうは、大好きな”ちゅ〜る”もいらないという状態でした。
療養用のゲージを準備し、寝床とトイレ、ごはんとお水をセットしなるべく安静に過ごしてもらうように環境を整え、強制給餌は3〜4時間おきに行うようにしました。
私は以前、実家の15歳の半野良の三毛猫(糖尿病、腎不全)の看病をしていたことがあります。
その子には、主に通院による点滴と少しの強制給餌を行っていました。
強制給餌といっても、嫌がる猫の口内に”ちゅ〜る”を無理矢理指で入れる程度。
シリンジを使っての給餌はしたことがありませんでした。
まずは、YouTubeでシリンジによる強制給餌の方法を勉強しました。
強制給餌に必要なものは、
- 給餌用のシリンジ
- ペースト状のごはん
(我が家では主にa/d缶を使用していました。) - 水を入れたスポイト
- 大きめのバスタオル
- 濡れ布巾
- 暴れる子には洗濯ネット
です。「かりんとう」は抱っこが嫌いで暴れるので、大きいタオルケットで顔以外の身体をしっかりと包み、バスタオルで首周りを包んで固定した状態で、人間の足の間に挟んで行いました。
自分1人で行う時は、猫を抱えた状態で背後からシリンジで給餌を行います。
2人で行うときは、1人が猫をしっかりと抱えて、もう1人が前から給餌をしていました。
どの方法が良いかはわかりませんが、誤嚥に注意しながら心を鬼にして給餌を行いました。
給餌用のシリンジはネット通販で買うことができます。
私は初めはこちらの10mlを使用しましたが、最終的には30mlのものが一番やりやすかったです。
ヒルズのa/d缶はこちら、
少量で高タンパク・高エネルギーを摂取することができます。
ペースト状で、シリンジにも入れやすい形状です。
DCMやペットショップにも売っていました。
普段食べているドライフードをふやかして、ペースト状にして与える方法もありますが、準備が大変なのと、必要栄養量をなるべく少量で摂取させるにはa/d缶がベストだったと思います。
強制給餌を始めた頃

ペットへの強制給餌には、賛否両論あると思います。
もちろん、嫌がるペットに無理矢理に強制給餌をすることは心が痛みます。
しかし、食べないままにするにはデメリットが多く、愛する我が子との別れに繋がりかねません。
「かりんとう」の状態は、肝リピどーシス(脂肪肝)が疑われ、薬だけでは治すことはできず、強制給餌が必要で、迷っている場合では無い状態でした。
強制給餌を始めた頃の「かりんとう」は、体力も落ちていて体重も軽く、割と簡単に捕まえることができ、シリンジでa/d缶を給餌することができました。
飼い主側がシリンジの使い方に慣れておらず、恐る恐る行っていたこともあり初めのうちは10mlのシリンジを1本あげるだけでも時間がかかりました。
でも、「かりんとう」は口に入れると嫌がりながらも「にゃむにゃむにゃむ…」と言いながら飲み込んでくれました。味はあんまり好みではないようす。
まずは1回あたりの給餌で、a/d缶の4分の1量をあげることを目標にしました
- 朝7時
- 仕事帰宅後の17時
- 夜21時
- 夜23時
のような感覚で初めの頃は給餌を行いました
お水は自分で飲む事は出来ていた(足りないですが)のが心の救いでした。
夜間に何も栄養を摂れない事が心配だった私は、深夜2時、早朝4時などに起きて、生猫用のミルクをあげていた事もあります。
当時は割と簡単に捕まえる事ができた(ぐったりしていた)ので、私も頑張っていました。
「かりんとう」も夜中に何度も起こされ、ミルクを飲まされ、疲れたと思います。
そんな日々を1週間ほど続けていると、ある朝、”ちゅ〜るを口元に持っていきあげてみると、自分からペロペロと食べてくれることがありました。
それを見た瞬間は、とても嬉しかったです(涙)
夜間、何が起きるか不安でほとんど眠れない日々が続いていたので私自身の意識も朦朧とする中での嬉しい出来事でした。
共働き夫婦なので、仕事に出かけている間が心配で心配でたまらなかったです。
この時ほど、「かりんとう」に食い意地があってよかった。
食に対する執着がハンパない、食いしん坊でよかった…と思いました。
セカンドオピニオン

強制給餌と服薬を初めて約1週間経ち、早朝に”ちゅ〜る”1本は食べてくれるようにはなったものの、なかなかウェットフードやカリカリは食べれない日々が続いていました。
当時は、大好きなウェットフードを目の前に見せても匂いを嗅ぐ事すらしませんでした。
唯一反応してくれたのが”ちゅ〜る”でした。
トイレは自分ですることが出来ています。
ほとんど食べれていないこともあり、便は4日に1度ほど少量でした。
尿量は多かったですが、嘔吐などは無かったです。
飼い主側も給餌に慣れ、短時間で1回量を給餌することができるようになってきていました。
しかし、自力でご飯を食べることができないままでいる「かりんとう」をどうしてあげればいいのかわからなかった事と、自分達も仕事が忙しく体力的にも厳しかった事から、家の近くの獣医さんに相談をしに行きました。
最初に行った病院は待ち時間が長すぎる事と、診察方法が私たちには合わなかったので、セカンドオピニオンも含めて近所の獣医さんにかかってみることにしました。
以前、「くりきんとん」のワクチン摂取をしてもらった、車で10分の獣医さんです。
優しい先生と受付の薬剤師兼看護師さん?のいる町の獣医さんのようなところでした。
先生に今の状況と、先日の血液検査と初見を説明し、「かりんとう」を診てもらうと、黄疸と口腔内の酷さに驚いているようでした。また、肝リピドーシスの診断があることを伝えると、「確定診断は細胞検査をしないとわからないよ。」と言われました。
私はその事実を、この場で初めて知りました。
初回受診した獣医さんも知ってはいたと思いますが、「かりんとう」の状態からは検査ができず、憶測で診断してくれたのだとは思います。
今回はセカンドオピニオンを受けたかったことと、もう一つ、経鼻栄養の相談をしたくて獣医さんを訪ねたのです。
私たちは強制給餌を続ける中で、ネットでいくつもの症例を読み漁り”経鼻栄養”という栄養摂取の手段が、肝リピドーシスを患う猫の治療法の1つにあることを知りました。
ですが、こちらの獣医さんは経鼻栄養にはあまり乗り気ではないようでした。
きっと、猫にとっては辛いものだとか、チューブをつけても外してしまいうまくいかないケースが多いと理由だったのだと思います。
緊急事態の「かりんとう」の処置を悩んでいたところ、先生より「一か八かにはなるけれど、少しステロイドを打ってみる手はある。リンパ系が原因の胆管炎であればステロイドが効いて食べれるようになってくると思う。」と提案がありました。
ただ、ステロイドには腎臓に負担がかかるなどの副作用もあります。
『一か八か…』という言葉を聞いて悩み、決断することができずにいると
「兎にも角にも、今すぐに何かしてあげないと、この子の状態はマズイよね」と、先生に言われました。
人間に、猫の言葉はわかりません。
でも、「かりんとう」が辛そうにしていることと生きようと頑張っていることはわかりました。
どうしてあげることが正解なのかは、何回小さな命を看取ってもわからずにいます。
私たちは、一か八かの期待を込めて、ステロイド注射をしてもらうことにしました。
どうか、良い方向に傾きますように。と願いを込めて。
〜続く〜

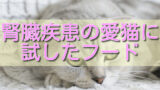


コメント